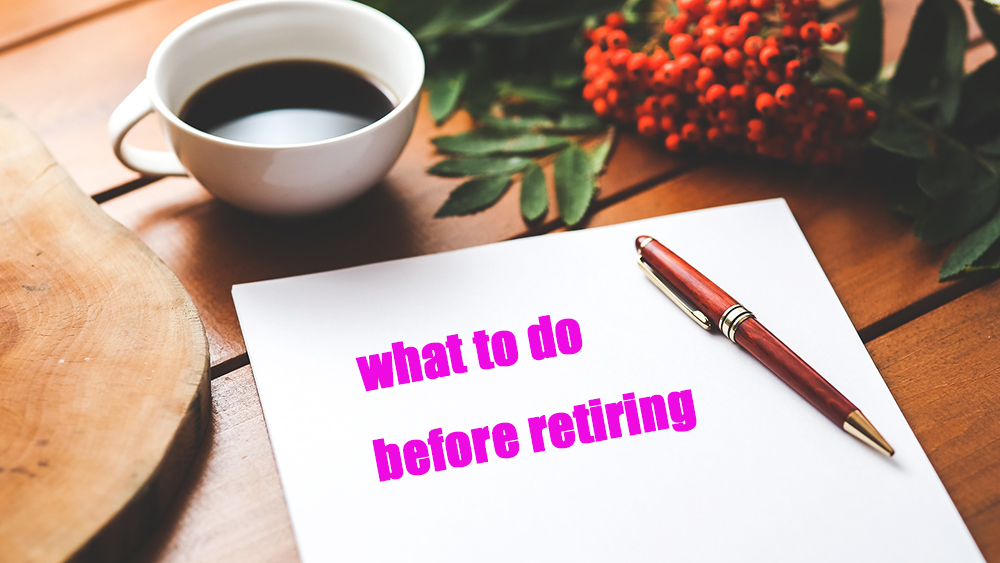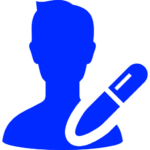
私が退職前に準備したことと
逆にやっておけば良かったことを
参考に載せておきます。
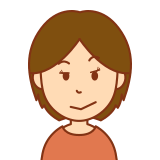
役に立つこと書いているかしら?
まぁ、読んでみましょうか。
退職前にやるべきこと
退職の意思表示
いつまでに言うべきか
退職の意思表示はいつまでにすればよいのか?というのは退職準備を進めていく上で悩むところではありますが、民法上では「退職希望日の2週間前」までに退職届を出せば退職出来ると定められております。
けれども、2週間前に伝えてサッと辞めていくというのはなかなか難しいもので、一般的に退職の時期に関しては、引継ぎや後任の選定などの猶予を勘案して、会社側の就業規則により定められており、多くは「退職希望の1~3か月前」程度が目安のようです。
私の場合は、かなり早めの1年前から退職の意思を伝えておりましたが、そこまで猶予を持たせなくとも就業規則に則って退職計画を立てていくのが良いと思います。有休が残っている場合は、その消化もプラスアルファに入れて計算していきましょう。
口頭か書面か
退職意思を口頭で伝えるか、書面で伝えるかの法律的な決まりは特に無いようです。
私の場合は、最初に直属の上司に口頭で伝えておりましたが、早く伝えすぎたせいか退職の話が無かったことのようになっていたり、再度意思表示をしてもダラダラとした引き止め工作にあったりと、口だけでは本気度が伝わり難いのか、本格的な退職準備に進むことがなかなか出来ませんでした。
最終的にはっきりとした退職意思を示す為に書面で伝えました。就業規則に則った方法でもあり、書面で伝えることで会社の上層部への打診など急に事態が動き出したので、最初からそうすれば良かったと思いました。
口頭では「言った、言わない」という問題も生じるかもしれませんし、証拠も残らないので、退職意思は書面で伝える方が良いと思います。退職意思が口頭か書面かは、会社により就業規則に定められている場合もあるので、退職を決意した時には確認してみて下さい。
「退職願」か「退職届」の作成
退職意思を書面で出す場合には、「退職願」か「退職届」を作成して提出します。どちらを作成するのかは、退職者の状況や、会社の就業規則の定義にもよりますので、ご自身のケースをよく確認して作成して下さい。
- 退職願
自らの退職意思を「お願い」という形で会社に申し出るもの。会社側の合意を得て、退職手続きに移行できる。会社が受理し承諾を得るまでは、撤回や交渉の余地がある。 - 退職届
自らの退職意思を正式なものとして会社に通知するもの。会社の同意や承諾に関係なく、会社が受理した時点で退職手続きが進められる。原則、受理後は撤回することが出来ない。
私の場合は、退職を願い出て会社の合意を得た上で円満に退職したかったのと、就業規則に「退職願」での提出が明記されてあったので、会社のフォーマットに則って作成し、提出しました。
業務リストの作成と引継ぎのスケジューリング
業務の引き継ぎは、自らの通常業務と並行しながら行うことになると思いますので、自分のスキマ時間で如何に準備し実行していくかが肝要になります。自分の時間だけでなく、引き継ぐ相手の都合もあるでしょうから、業務をリスト化し、引継ぎ時間をスケジューリングして、効率よく進めることが大事です。以下は私が引継ぎで行った方法になります。
- 業務の洗い出し
自分が行っている日次、週次、月次、年次別業務と随時発生するイレギュラー業務をそれぞれ洗い出します。毎日のルーチン業務、週1の報告書作成、月1の会議の進行や議事、年数回のクライアントや取引先との会合、等々自分の責任範囲で行っている全ての業務を漏れなく洗い出していきます。 - 業務リストの作成
洗い出しが終わったら、エクセル等で自分の全仕事をリスト化していきます。
私は後任がそのまま活用できるように、エクセルでかなり詳細なリストを作りました。
エクセルの1シート目に日次、週次、月次、年次、随時別の全業務リストの表を、2シート目に1日の時間割とルーチン業務、3シート目以降に週次、月次、年次、随時の業務の詳細を載せ、各シートの項目やマニュアル等をリンクで繋げるといった具合に作成しました。
Officeやその他アプリに詳しい方はもっと良いやり方があるでしょうから、それぞれもっと便利なリストを作成して下さい。 - マニュアルや資料の作成
口頭や簡単な資料では引き継げないものは、別途マニュアルを作成します。もともとマニュアルがあるような業務や、仕様書などの資料があるものは、そのまま業務リストにリンクさせて活用します。業務の引き継ぎは時間がない中で行うので、マニュアルまで作るのは大変ですが、後任者が困らないようにする心遣いも大事だと思いますので、可能な限り用意すると良いです。 - 引き継ぎのスケジューリング
1日で全仕事を引き継ぐことは無理でしょうから、自分の時間と後任者の都合を考慮しながら、落とし込む項目を、日時単位でスケジューリングしていきます。相手の意向を確認しながらスケジューリングすることが大切です。
余談ですが、私の職場はシフト制でしたので、互いの休みがズレていた関係で数日会えないこともあり大変でした。最後の方は後任者のシフトを自分のシフトと同じにしてもらって乗り切りました。 - 業務のOJT
後任が決まり引継ぎをする時期にもよりますが、口頭やマニュアルでの引継ぎだけでなく、出来ればその人が自分の業務を一人称で出来るように、横について実際の業務を体験させることが好ましいです。後任者も不明点をその場で聞けるので安心でしょうし、何よりも退職後に質問の電話等が来て、元の仕事に引き戻されるのも煩わしいので、自分の為にも可能な限りOJTは行った方が良いでしょう。
挨拶リストの作成
退職の挨拶のタイミングは特に決まっていませんが、退職日の1か月以内で会社のメールや電話が使える内に行う方が良いと思います。また、後任が決まってからの方が挨拶の中で紹介も出来るので、二度手間にならずに済みます。
私は、引き継ぎと同様に挨拶リストも作成して、仕事の付き合いの密度や頻度により挨拶のスケジューリングをしました。長い付き合いのあるクライアントや取引先等は、自分が在職している間に依頼したいこともあるでしょうし、もしかしたら送別会のようなものを設定してくれるかもしれませんので、逆に余計な気遣いをさせないよう早めに伝えました。メールや電話ではなく、会社に挨拶に出向く場合も日程調整が必要ですので、早めに知らせた方が良いでしょう。退職までの最後の1か月はバタバタと慌ただしく過ぎるので、挨拶リストとスケジューリングは大切だと感じました。
身の回りの整理
ある程度の年数会社に在籍すると、意外に身の回りのものは多く溜まっているので、退職の日までに意識して片付けていくことが良いと思います。わたしの場合は「退職の日」でも書きましたが、出勤最後の日まで片付けが終わらずに大変な思いをしました。
会社に返却するもの、私物で持ち帰るもの、社外秘や個人情報等社内ルールに則って処分するもの、資料として人に渡せるもの、後任に引き継ぐもの、と仕分けしつつ、残りの業務で使わないものからどんどん片付けていきましょう。油断していると私のように最終日に残業する目に合います。
また、職場によっては大型ごみや資源ごみ等の分別ごみのスケジュールがあります。退職時の身の回りの整理には大量の廃棄物も出ますので、ごみ出しスケジュールも確認しつつ片付け作業を行うと、退職後に職場の人に迷惑をかけ陰口を叩かれることもないと思います。
メールやOfficeで作った資料、チャットの履歴、社内クラウドの保管データ等、パソコンのデータ上の片付けも忘れずに行いましょう。会社によってはデータの処分方法が定められている場合がありますので、ルールを確認してから行って下さい。
これまた余談ですが、私には、必要な時が来るかもと処分しきれずにいたメールやデータがかなりありましたが、もう自分には関係ないとごっそり削除出来た時は、憑き物が落ちたような爽快な気分になりました。社内パソコンはメモリーにも社内クラウドにも何もない状態を確認した上で、リセットして返却しました。
退職前にやっておけば良かったこと
転職エージェント会社との契約
私の場合は、日々の業務に追われ過ぎて時間的にも精神的にも、退職に向けた行動をするだけで精一杯でした。後のことは退職して十分に休養してから考えようと思っておりました。
退職して休養後、さぁ転職活動を始めようと、転職エージェントに登録しましたが、転職業界の最前線で仕事をしているエージェントから聞く話は、ミドルの転職者にはとても厳しいものでした。
自分のスキルと年齢と残された人生の就労可能期間から採用企業が何を求めているのか知る為、雇用人材としての自分の価値と現在地を客観的に把握する為、在職中に転職エージェントに登録して、事前に情報を得たり、相談できる環境を作っておいても良かったかなと思いました。
「退職の決意」までの私の転職ブログで書いた通り、私は職場に残るつもりはなかったので、在職中に転職エージェントからアドバイスをもらっていたとしても、思いとどまることなく期日通りに辞めていたでしょうが、登録して準備しておけば退職後の転職戦略は少し変わっていたかもしれません。
私が登録した複数のエージェントについてや、話の内容についてはまた別の機会に記述したいと思います。
転職活動(出来れば内定)
退職後、休養を取って一旦リセットしてから働こうという場合は別ですが、在職中に転職活動をして、出来れば次の仕事の内定を取っておくことは、生活の不安を抱えず生きていく為に、健全で現実的なことだと思いました。
私は働きながら転職活動が出来るような環境や状態ではなく、退職後の時間的余裕の中で、どう働きたいのか、何をしたいのかを決めるしか道はなかったと、今でも思うので後悔はしていませんが、もし働きながら転職活動が出来たのであれば、そうしていたかったと思います。
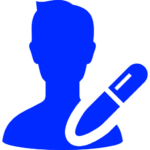
いかがでしたでしょうか?
私の退職準備は至らないところもありましたが、
退職時に慌てない為にも準備は大切だと思いました。
読んでいただき少しでも参考になったなら幸いです。
退職後のことや必要な手続き等は、またブログに載せていきます。